こんにちわ!ムッシュです!
投資家としてはやっていくことは高配当とインデックス投資を続けること
私のインデックス投資はiDecoだけでオルカンとSP500のemaixm slimなんですが
高配当は個別株を買って自分でポートフォリオ作ってやってます
インデックスは正直やることないので放置です、見てもないですねw
高配当投資は金の卵を産むニワトリを育て増やす行為。元気で末永く金の卵をドンドン産んでくれるニワトリを選ぶのが銘柄選び!
高配当投資は何といってもこの銘柄選びが重要!
そこで私の銘柄選びをお伝えしようと思います。銘柄選びは少しずつでも変化を加えていったほうが良いと思います。勉強を常に続けているといろいろなことがわかってきて「どういう行動をとる」かの手札が増えていきますし、前まで正しいと思ってことが間違いじゃないかと思う時もあります
そう意見は変えていいんです!w
ではいきましょう!
上場から10年以上経ってる

会社を上場させるのは非常に大変です
なのでそれを目標にしている経営者も多いですが、残念ながら上場はゴールではないです
連載漫画が良いところで突然終了するのと似てますねw
上場で燃え尽きて継続できない会社も多くありますがそれを見抜くのは一般人には至難の業です
なので上場して10年生き残れた会社はビジネスモデル、収益・財政の健全性、経営者の手腕など一定以上のレベルに達してると判断してます
新規上場した会社が10年以上残るのは大体3~4割と言われてます
投資は長期で行うもの、長期で存続してくれないと意味がありません
売上高

なんといっても利益の源泉は売上高、そしてその利益から配当金は支払われます!
そこが不安定や減少傾向にあっては意味がないでしょう
なので金額はさておいてある程度の範囲の中で安定しているか、多少波があっても増加傾向かを見てます
特に上場10年ギリギリの企業は売上高は増加傾向でないとその企業の商品やサービスが普及してないことになります。企業の先行投資期間中でマイナスになっている時に上場するのも良いかもしれませんが、私がしているのは長期の高配当投資その状態で配当金の安定支払いはできないと思います
EPS
企業の収益性を測る指標の一つで、1株あたりにどれだけの利益が生み出されているかを示すものです。
つまり、EPSが高いということは、その企業が1株あたりに多くの利益を出している、
言い換えれば収益性が高いということを意味します。
これが増加傾向か、安定しているかを見ます
経営や配当金の安定度合や今後増配してくれる期待が高いです
営業利益率
営業利益率とは、企業の本業の収益力を示す重要な指標の一つで、売上高に対して、どれだけの営業利益(本業から得られた利益)が出ているのかを示す割合のことですね
簡単に言うと、企業が本業でどれだけ効率的に利益を出せているかを表すものです
これが業種平均以上であることが条件です
この「業種平均」というのがポイントですね
業種によって利益の出しやすさは違います
市場全体では4%が平均ですかね
なので営業利益率4%以上を条件に出している投資家の人もいますが
業種平均の営業利益率が6%なら5%は低いですが4%以上です
業種平均が2%なら3%でも高いですが4%以下です
もちろんもっと細かく見ないといけないですがキリがないので業種平均を目安にしてます
これからは人手不足、人口減少になる日本ではいかに効率よく稼げるかが大事になってきますので、より重要度が上がっている条件ですね
自己資本比率

企業の財務の安定性を測る上で非常に重要な指標の一つです。
企業の総資産のうち、自己資本がどれくらいの割合を占めているかを示すもので、「会社の自己資金でどれだけ賄われているか」を表しています
これが低いという事は負債が多いということです。いわば借金です。借金には返済義務があり利子も払わないといけません。業績も関係なく払わないといけないものが多いというのは経営的に不安定と言わざるを得ない
なので私は自己資本比率40%以上を目安にしてます
ビジネスの開始直後なら自己資本率は低くなることはありますが、最初の条件である「上場してから10年」がありますので10年経っても自己資本率が低いままというのは長期投資しにくいですし、常に監視する必要があるため正直めんどくさいです
会社設立してから上場するまでにもある程度期間があるため、実際は設立から10年以上経っているのにも関わらず借金まみれということですからね
大きな投資をして一時的低くなることもありますが、それは場合によるという感じですかね
例えば元々50%だったのが39%になったというのであればそこまで大きなものではなく投資(挑戦)とも取れますが、80%が20%になったという感じならそれは投資(挑戦)ではなく博打です
そんなところには付き合いきれません
※金融関係はビジネスモデルの特徴として、とても低くなってしまうのは仕方ないので、金融関係は自己資本比率は見ないです
営業CF
営業キャッシュフロー(営業CF)とは、企業の本業である営業活動によってどれだけの現金を生み出しているかを示す指標です。
簡単に言うと、企業がどれだけお金を稼いでいるかを、現金の流れという観点から表しています。
なぜ営業CFが重要なのか
- 企業の真の実力: 利益は、売上高から費用を差し引いたもので、必ずしも現金化されているとは限りません。一方、営業CFは、実際に手元に入ってきた現金を示すため、企業の真の実力を測る上で重要な指標となります。
- 資金繰り状況: 営業CFがプラスであれば、本業でしっかりと現金を生み出しており、資金繰りが安定していると考えられます。
- 将来の成長力: 営業CFが安定してプラスであれば、その資金を設備投資や研究開発に充てることができ、将来の成長につながる可能性が高まります。
営業CFは企業の売上回収能力とい言っても良いでしょう
売上高はあるのに回収能力が低い会社が次々潰れたのがリーマンショックです。黒字倒産ってやつです。会計上だと売掛金はたくさんあるのに現金はないという状態ですね
そして当然その中から配当金がでますので営業CFは非常に重要な条件です
私は営業CFが常にプラスになっている企業しか選びません
売上を確実に現金化する仕組みがあるという事ですからね
少なくとも直近10年はプラスでないとダメですね。企業も良くなるので以前ダメでも今は良くなってるパターンがありますから
現金
配当金も設備投資も企業に自由に使えるお金がいくらあるかにかかってます
貸借対照表上の現金が安定しているのは最低条件、ビジネスが堅調なら多少の波があっても増加傾向にあるはずです
なので現金の残高が増加傾向にあるのが条件で、最短でも過去10年は増加してないとダメですね
ぶっちゃけていうと現金が無限にあれば企業はいくらでも存続可能なのです
設備投資しようが何をしようが現金があればどんな無茶をしてもそれは博打にならず挑戦となります
何度も言いますが高配当投資は長期投資です。長期の存続できる会社を選ぶのが大事
配当性向
配当性向とは、企業が利益の内どれくらいを株主に配当として還元しているかを示す指標です。
自分達が稼いだお金を株主にどれだけ渡す気があるか、どれだけ渡しても経営として成り立つかを示しています
計算式は以下の通り
配当性向 = 配当金額 ÷ 当期純利益 × 100
これが40%前後が健全で70%以上は高すぎるという感じです
配当金多く払ってくれるなら良いじゃないかって思うかもしれませんが会社が得た利益を会社が得るか、株主が得るかで極端な話、配当性向100%だと株主が全部の利益を得るとなると、会社は成長や維持、何かあったときの資金が無いのは健全でないと思います。よって40%前後が健全と判断しました
あまりにも低すぎるのは株主還元の意志無しか経営が怪しい可能性があると判断してます
今はDOE(株主資本配当率)に配当方針を変更している企業も増えてきてますね
これは営業利益率と同じように業種平均で見るのが正しいかと判断してます
DOEの場合配当は安定しますが反面、業績が良くなってもそこまで配当には影響しなくなりますので良し悪しありますね。増減配の幅が小さくなるといったイメージですかね
詳しくはDOEって何?をご覧ください
あと配当方針が配当性向またはDOEまたはその他合理的な理由や計算で出されるものであれば良いのですが、「総合的に考えて出す」といった配当方針が抽象的や曖昧な表現の所は外します
株主還元に責任感を感じないからですね。意思決定をするのが経営者の役割でそれをその場の思い付きでどうにかしようとしている感が個人的に嫌いでもありますし、いつでも減配するってカードを責任なく切れる状況なのは安定の配当を得たい私としては避けたいところ
配当利回り

高配当投資家なら気にならない人はいないでしょう
配当利回りは投資金額(簿価)で見る人と時価で見る人に分かれると思いますが
私は投資金額で見る人です。推測ですが時価で見る人は短期で売買することを考えているのかと思いますが私は長期投資で基本ほったらかしなので投資金額(簿価)で見ます
配当利回りは厳しめの税引き後で4%です
NISAなら比較的簡単ですが特定だと5%はないと税引きで4%にならないのでリスクは高いですね
その分銘柄選びが厳しいので大丈夫であろうと思ってます
ただし増配傾向が顕著で毎年増配をしているなら税引き後3.5%でもありとしています
その内に税引き後4%以上に到達すると見込んでいます
決算資料
これまでの条件はyahoo配当利回りランキング・証券アプリ・IRバンクなどで比較的簡単に見ることができます
その条件をクリアした企業のHPに行きIR情報や事業内容を見ます
今までの条件をクリア ⇒ 決算資料 という流れです
決算説明会用の資料が見やすいですね
中にはこれが非常に雑な企業、わかりにくい企業、さらには5年以上前で更新が止まってる企業もあるのでそういう企業の性格みたいなものも推し量れる材料になります。長く付き合う相手とは気持ちの良い関係でいたいですからね
株主に見せる資料がわかりにくいものでも良いというのは、情報を伝える力が低いということですし、顧客のことを考えて事業をできているか疑問に思います

あとIRバンクでは見れないのが流動資産比率
企業が1年以内に現金化できる資産(流動資産)が、1年以内に返済しなければならない借金(流動負債)をどれだけカバーできるかを示す割合のことです。
流動資産比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
流動資産比率が2以上で文句なし、最低でも1.5以上でないとダメです。
1年以内に返済しないといけないお金は十分に返すことが出来る状態なので、短期での財務安定性の目安になります
適正な比率は業種によって異なるんですが、ここはセオリー通り2以上であれば良いかと思います
あくまで短期の目安なので買う時に確認する程度ですね
私の高配当株投資のやり方で損をするのは購入直後に減配などで条件に外れる時で、株価が値下がりしているし、配当金もほぼない状態なので惨敗という感じですね
その状況になりにくくするにはこの短期での資金繰りの目安として流動資産比率が大事になってきます
企業も自分たちは無能と思われたくないため減配はしたくないと思います。現金に余裕があるなら減配する可能性は低いです
ただ減配する時はするのであくまでその可能性を低くするということですね
例外
何事にも例外はあります
自己資本比率の時の金融関係のようなものです
それは〇〇ショックの時は除外するということ
もちろん〇〇ショックの時でも揺るがないのは評価しますが、そんなときでも売上高は維持しろ営業CFはプラスでないとダメだ!などパワハラ上司みたいなことは言いませんw
天変地異もありますし戦争もあります
それに巻き込まれたのを企業の責任にするのは酷なものです
最後に
いかがだったでしょうか?
条件や意見は変えるとブレているようにも見えるかもしれません
初志貫徹や一貫性のあるものは確かに素晴らしいと思います
でもそれは裏を返せば「絶対間違ってはいけない」とも言えます
私は大した人間ではないので絶対間違えますw。なので常に向上心を持ってより良いものにブラッシュアップしていくのです
この銘柄選びがあなたの一助になれれば幸いです!
最後までお読みいただきありがとうございます!
Fire目指して頑張っていきましょう!!


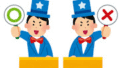
コメント